近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、士業を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。
「AIで専門職の仕事が奪われるのでは?」という不安の声もある一方で、士業の知見×生成AIという組み合わせこそが、真の価値を生み出す時代へと突入しています。
本記事では、弁護士・税理士・社労士などの士業が、生成AIと共存・活用しながら、自身の価値を最大化できるオンラインサロンの設計ポイントをご紹介します。
1. なぜ今、士業にオンラインサロンが必要なのか?
士業は従来、紹介や信頼で成り立っていた業界ですが、時代とともに「情報発信力と共感形成力」が求められるようになっています。
また、生成AIの台頭により、単なる「情報の提供」だけでは差別化が難しくなっています。
オンラインサロンを持つことで、
- 継続的なファンとの接点が作れる
- 自身の専門性に共感するコミュニティを育てられる
- AIでは対応できない「背景」「文脈」「実務」の共有が可能になる
といった形で、「AI時代でも選ばれる士業」へと進化できるのです。
2. 生成AIを取り入れたオンラインサロン運営のヒント
士業オンラインサロンに生成AIを活用する具体例としては、以下のようなものがあります:
- ChatGPTによる一次的な情報整理→サロン内での実務的補足解説
→ AIは概要まで、深掘りは専門家が担う役割分担が可能です。 - AIを活用した定期レポートの作成・配信
→ 最新の法改正や判例などをAIで速報化し、士業目線で解説するなど。 - メンバーの質問履歴をもとにAIがナレッジ化し、Q&Aを自動分類
→ コミュニティの資産が蓄積され、再利用も可能に。
AIが単独で対応できない“人間的価値”を、サロンを通じて伝える設計が重要です。
3. 共感と信頼のデザインが鍵
オンラインサロンは単なる情報提供の場ではなく、「価値観の共有」「問題意識の共有」が起点となります。
AI時代だからこそ、人間の感情に訴える「共感」が差別化の鍵となるのです。
- なぜこの専門分野を追求しているのか?
- どんな人の役に立ちたいのか?
- どんなビジョンを描いているのか?
これらをストーリーとして丁寧に発信できるサロン設計が、AIとの共存・共栄の第一歩となります。
4. オンラインサロンを始める前に決めるべきこと
士業がオンラインサロンを設計する際には、以下の4つの軸を明確にすることが大切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | ブランディング?収益化?仲間づくり? |
| 対象 | 一般向け?士業同士?特定業種? |
| コンテンツ形式 | 投稿・ライブ配信・Q&A・講座? |
| 運用リソース | 自分で運営?サポート依頼?頻度は? |
特に「AIで代替できない強み」を可視化する視点を持つことが、長期的な成功を左右します。
まとめ:生成AIと共存する士業の未来へ
生成AIは“脅威”ではなく、“拡張”のための道具です。
重要なのは、それをどう活かすか。
そして、「あなたにしかできない発信と関係構築」をどう設計するか。
日本士業サロン制作合同会社では、士業の専門性と人間性が伝わるオンラインサロン設計・運営支援を一貫して行っています。
生成AI時代に選ばれる専門家になるために、今こそ一歩を踏み出してみませんか?

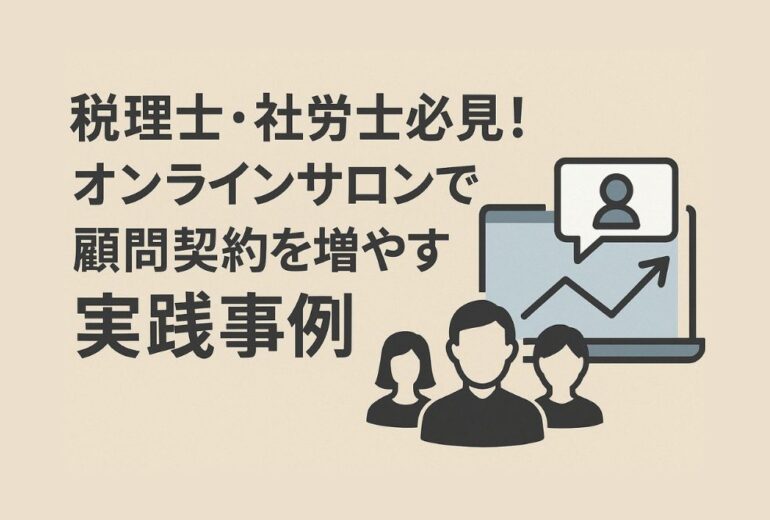

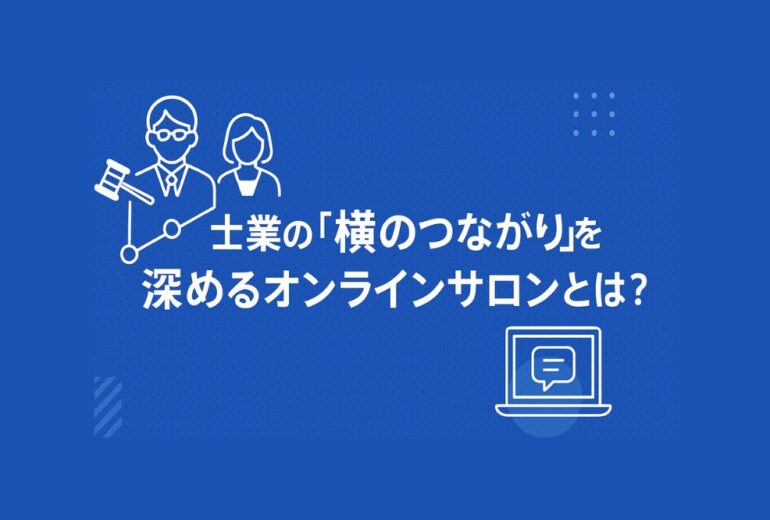

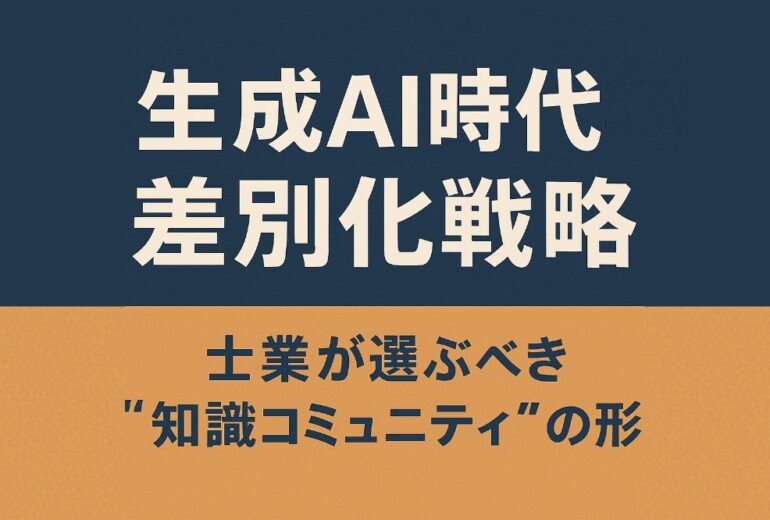
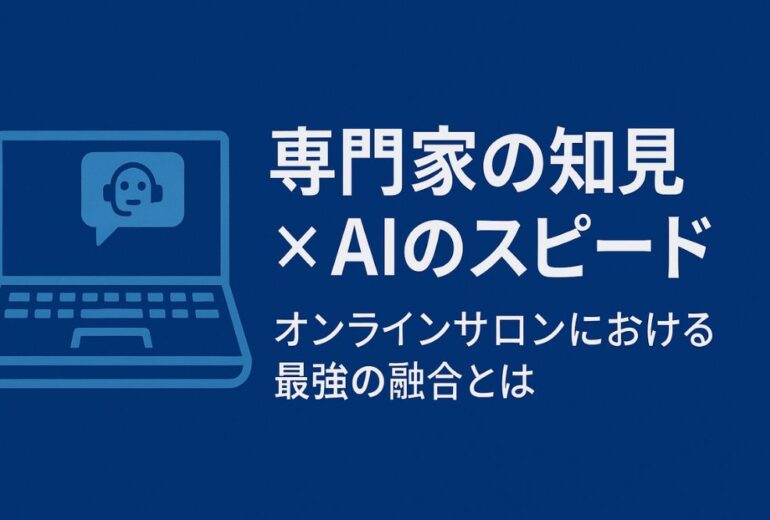

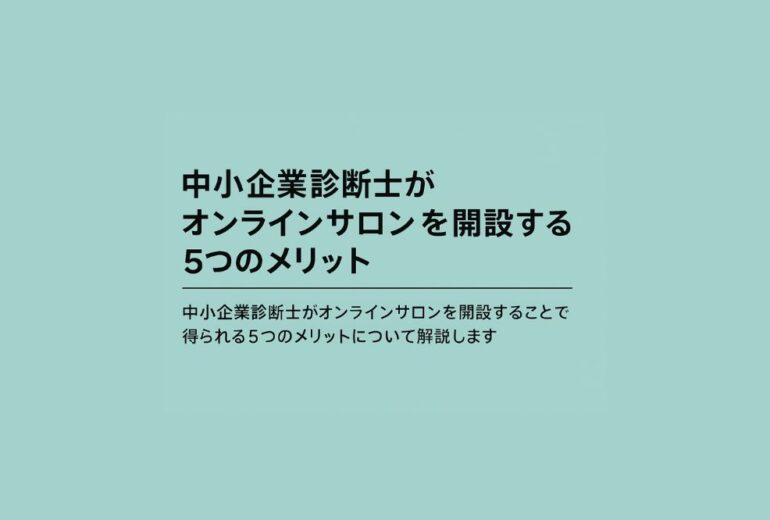
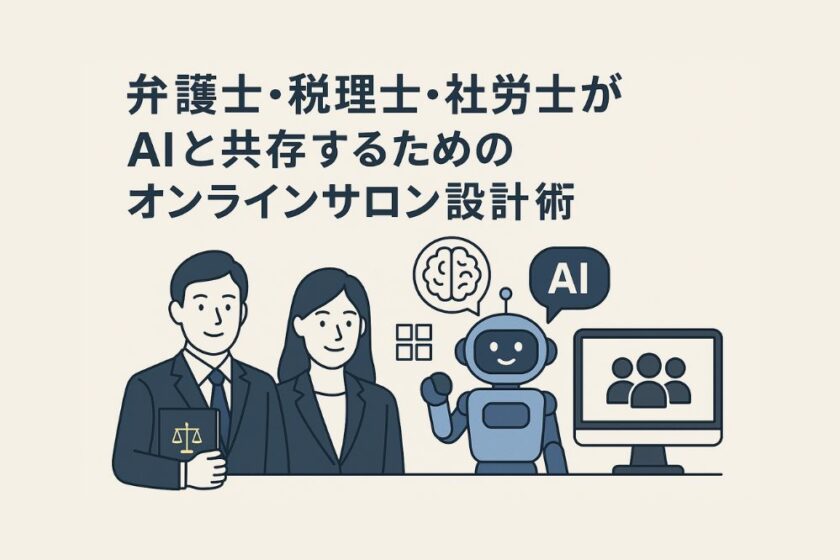
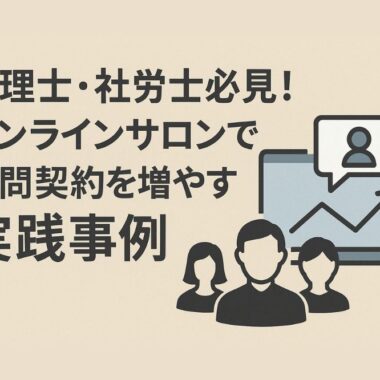


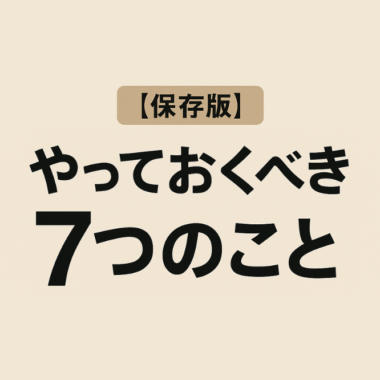
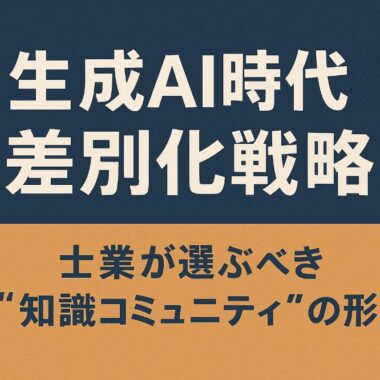
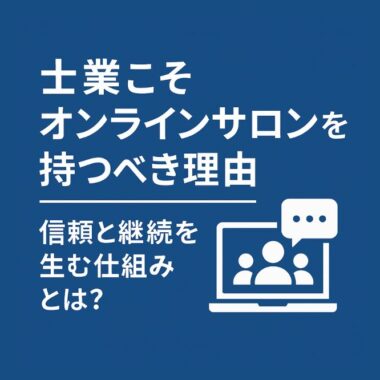



コメント